

株式会社フライクは「システムを用いて“できない”を“できる”にする」を合言葉に、社内システムの構築や設計、導入、改善など、企業の経営戦略にまで踏み込んだ支援を行っているスタートアップです。
現在、第二成長期を見据え、未経験を含めた人材の積極採用を進めている同社。今回は代表取締役の大瀧龍さんに、業務を進めるうえで大切にしている考え方について伺いました。
フライクは「安請け合いしない」をモットーとし、“物言う取引先”としてクライアントと対等な関係を築いているそう。そのことが働きやすさにもつながっていると、大瀧さんは話します。なぜフライクはお客様至上になりがちなビジネスの領域で、独自のスタンスを貫けているのでしょうか。その背景に迫ります。
日本におけるSaaSの導入成功率は52.8%。なぜ約半数のDXが失敗に終わってしまうのか
――過去のインタビューでは、これまでのキャリアについて伺いました。近年ではDXという言葉もよく耳にしますが、さまざまな業界とITを通じて接点を持ってきた大瀧さんは、このトレンドをどのように感じていますか?
大瀧:言葉だけが独り歩きしているような状況だと感じています。日本におけるSaaS導入の成功率は、52.8%にとどまっています。つまり、約半数のDXプロジェクトは失敗に終わっているんです。改善の余地が多分にある分野なのにもかかわらず、方法論だけにフォーカスが当たっている状態はとても歪ですよね。このことがまた成功率の低下を招くという負のスパイラルを生んでいる実感があります。
――なぜこのような低い成功率となっているのでしょう?
大瀧:DXという手段を目的にしているクライアント側と、売上を得たいばかりで適切な処置ができないシステムベンダーのあいだで、利害が一致してしまっていることがひとつの理由だと考えています。

大瀧:組織の状況を診断するときによく耳にするフレームワークとして「マッキンゼーの7S」と呼ばれるものがあります。「組織構造(Structure)」「システム(System)」「スタイル(Style)」「スタッフ(Staff)」「スキル(Skill)」「戦略(Strategy)」と、それらが結びついたときに浮かび上がる「共通の価値観(Shared value)」の頭文字を取ったこの言葉は、経営や組織改革の場面で広く使われています。
本来はこれらがすべて揃っていなければ、組織の課題解決はできないはずなんです。にもかかわらず、表面的なデジタル化のために双方の折り合いがついてしまっている。システムベンダーの一面も持つフライクの立場から言うのであれば、いくらクライアントの望みであっても、伝えるべきことは伝える必要があると感じています。
――とはいえ、どうしてもクライアントとは主従の関係になってしまいそうな気もします。
大瀧:そうなんですよね。その点が問題を複雑にしています。
フライクでも過去に似た事例がありました。クライアントはある大手企業で、社内システムのデジタル化を目指しており、実現してくれるシステムベンダーを探していたそうです。その一方で、業務設計にかかるヒアリングやコンサルティングは一切求めておらず、「私たちの作りたいシステムを構築してくれればそれで良い」というスタンスでした。
ご想像のとおり、結果は失敗に終わりました。そして、その1年後、メーカーからの紹介で再度フライクにお話が来たんです。そのときもクライアントの姿勢は変わっていませんでした。
お互いが納得する形で進められるよう話し合ったのですが折り合えず、最終的に契約をお断りしました。私たちにとっても気づきのある出来事でした。
――意義深いデジタル化を果たすのであれば、ただツールを導入するだけでなく、組織や戦略もシステムにあわせて変化する必要があるのですね。
大瀧:そのとおりです。システムには3つのタイプがあると言われています。「絆創膏型システム」「処方薬型システム」「漢方型システム」です。

大瀧:多くのSaaS導入が分類されるであろう「絆創膏型システム」は作業コスト/経済的コストがともに低く、取り組みやすい一方で、最も失敗につながりやすい傾向があります。一方、「漢方型システム」はハードルこそ高いですが、背景にある考え方が最も本質的で、導入が成功につながりやすいんですね。本来、DXはこうあるべきなのです。コロナ禍を経て、トレンドワードとなったことで、手段を目的化している企業が増えてしまいました。
マルチプレイヤーであることが無二のポジショニングに。“物言う取引先”として「知ること」を大切にしてきたフライク
――大瀧さんはSaaSの導入成功率を100%に近づけることが可能だと思いますか?
大瀧:正直難しいでしょうね。世にある多くの失敗例では、その要因が複雑に絡み合っており、点ですべてを語ることができません。導入効果が薄いとき、企業はその原因をシステムベンダーやSaaSそのものの不備としがちですが、実際には7Sの各項目が基準に達していない場合も少なからずあります。成功率を高めていくためには、各部門、各業界を横断したDXが必要となるでしょうね。
――そこで専門家による診断や分析、助言、指導が必要になってくる、と。
大瀧:はい。IT業界にはさまざまなプレイヤーが存在し、それぞれに役割・課題解決の手法が異なります。たとえば、SIerは現場でのスクラッチ開発を得意とし、SaaS企業はまるごと提供することを前提とした自社プロダクトの開発に特化しています。これらの各プレイヤーが7Sに代表されるクライアントの問題すべてに気づくのは難しいでしょう。彼らは一点に集中した専門家であるからです。ここにフライクの存在意義があります。
フライクは、スクラッチ開発だけを行うわけでもなければ、自社プロダクトの開発・導入を提案するわけでもありません。クライアントの課題に対し、業界や部門の区別なく、支援を行っているマルチプレイヤーなのです。これは各専門家に対し、技術や知識の面で引けを取るという意味ではありません。前提となる条件・能力を持ち合わせたうえで、横断的なDXに取り組める無二の存在がフライクであると、私は自負しています。

――SaaSの導入に関して、フライクが独自のポジションから気をつけていることがあれば教えてください。
大瀧:クライアントの考えに迎合し過ぎず、“物言う取引先”であり続けることに尽きますね。私たちは何百ものサービスを業務の内外で実際に触ってきました。それぞれについて、メリット・デメリットを把握しています。だからこそ、これらすべてが提案可能な選択肢となっています。お客様の希望に応じて最適なツールを選べる点、そしてそれを臆せず提案できる点がフライクの強みなのです。
また、フライクはfreeeやSalesforceなど、特定のサービスの代理店というわけではないので、それらに肩入れする必要がありません。本当の意味でお客様にとって最適なものを選び、提案することができます。過去には、あるサービスの導入を検討しているクライアントに「そのサービス、本当に必要ですか?」と思い切ってお話したこともありました。これはバリューのひとつにある「事業成長を支える唯一無二のパートナーでいる」にも通じてくる部分だなと思います。顧客視点かつ第三者視点で率直にお伝えすることが、結果としてクライアントの売上げ、生産性のために繋がってくると考えています。
また、フライクでは常時30ものITツールを自社内で導入・実践しています。研究や検証に手を抜いていないからこそ、自信を持って提案を行えています。
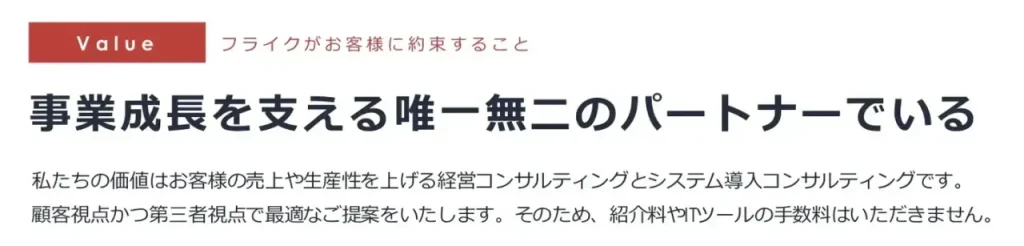
独自のスタンスを貫くことが、メンバーの働きやすさにもつながっている
――“物言う取引先”として課題解決に向かう姿勢を、クライアントからはどのように評価されていますか?
大瀧:「うちの従業員よりも、うちのことを知っているね」という言葉をよくかけていただいています。お客様を知ることに力を入れているフライクなので、このように評価されることはとても嬉しいですね。
私は、組織構造、業務、課題など、クライアントに関連するすべてのことを知らなければ設計はできないと考えています。適切な戦略を立てるためには、相手を知ることからなんですね。
フライクでは設計にあたり、お客様に2時間のヒアリングの機会をいただいています。そこで業務の表層だけにとどまらず、組織のことや感じている課題、ビジネスモデル、展開しているサービスなどについて、詳しくお話をうかがいます。なかには不必要と思われる内容もあるかもしれません。ですが、そういう部分にこそ、課題解決の糸口が眠っているんです。嬉しい言葉をかけていただけるのは、親身になって取り組み続けていることの結果だと感じています。
――「求めることだけをしてほしい」というクライアントとは、そもそも求めているサービスが違うのかもしれません。
大瀧:そうですね。フライクと良好な関係性にあるお客様は、どちらかと言えば「相談に乗ってほしい」というスタンスであることが多いです。私たちとしては、その方がより仕事に責任を持てますし、やりがいや面白さも感じられます。
――ミスマッチを避けるために、工夫していることはありますか?
大瀧:クライアントを「自己啓発型」「他己紹介型」「他社丸投げ型」という3つのタイプに分類して考えるようにしています。

フライクと最も相性が良いのが、1つ目の「自己啓発型」です。このタイプには、解決すべき課題に自ら気づけ、かつそれらに対し、自発的にアクションを起こせる企業が分類されます。「自己啓発」という言葉のとおり、高みを目指すために必要な思考と行動力を持ち合わせており、第三者の協力によって、より大きな推進力を持って課題解決に向かえる企業ですね。
一方で、ミスマッチになりやすいと考えているのが「他社丸投げ型」です。このタイプは、課題の発見と解決を第三者に委ねており、自発的にアクションすることが少ないです。先ほどお話ししたような「手段の目的化」に陥る傾向が強く、有能なパートナーが見つけられたとしても、良い結果に結びつきづらい特徴があります。

フライクは、「足し算」ではなく「掛け算」で課題解決に向かいたいと考えています。ITの力を通じ、クライアントの推進力をときに2倍、3倍にしていくのが私たちの役割だと思っています。当然、片方がゼロに近づけば、導き出せる答えもゼロに近づいてしまう。だからこそ、お客様には当事者意識を持って課題解決に臨んでほしいですね。
また、このようなスタンスを貫いているからこそ、フライクには独自の働きやすさがあると自負しています。過去のインタビューでお話した待遇の厚さ、ストレスフリーな環境は、こうした業務の進め方にも支えられていますね。
――最後に、求人への応募を検討してくださる方に向け、メッセージがあればお願いします。
大瀧:フライクは各業態で「できない」ことを横断して「できる」よう、クライアントと真正面から向き合い、そして伴走していることが本ストーリーから少しでも伝わっていたら嬉しいです。
今後一緒に働いていく方にもぜひクライアントの真の価値提供を考えながら、一緒に事業を手がけていただけると嬉しいなと思っています。







