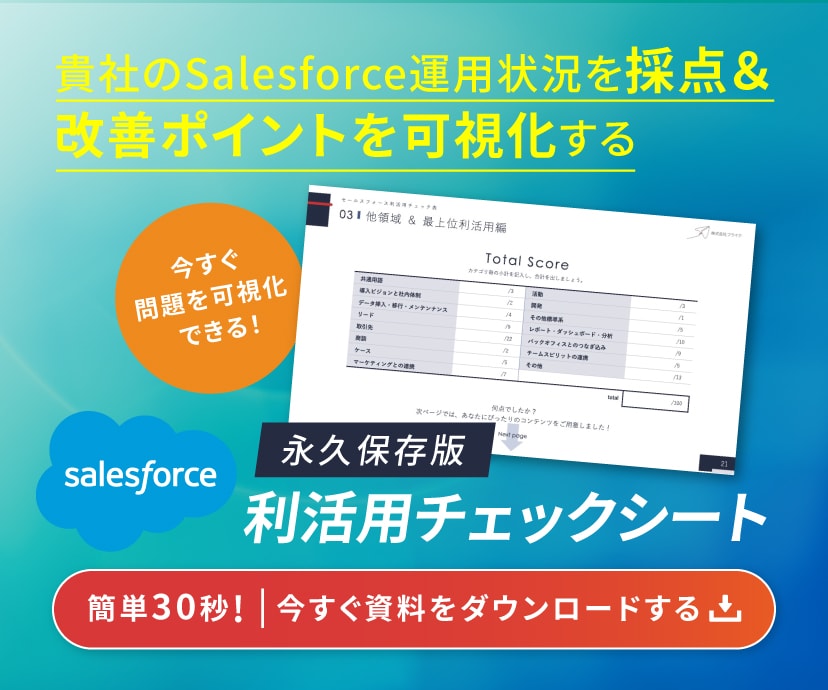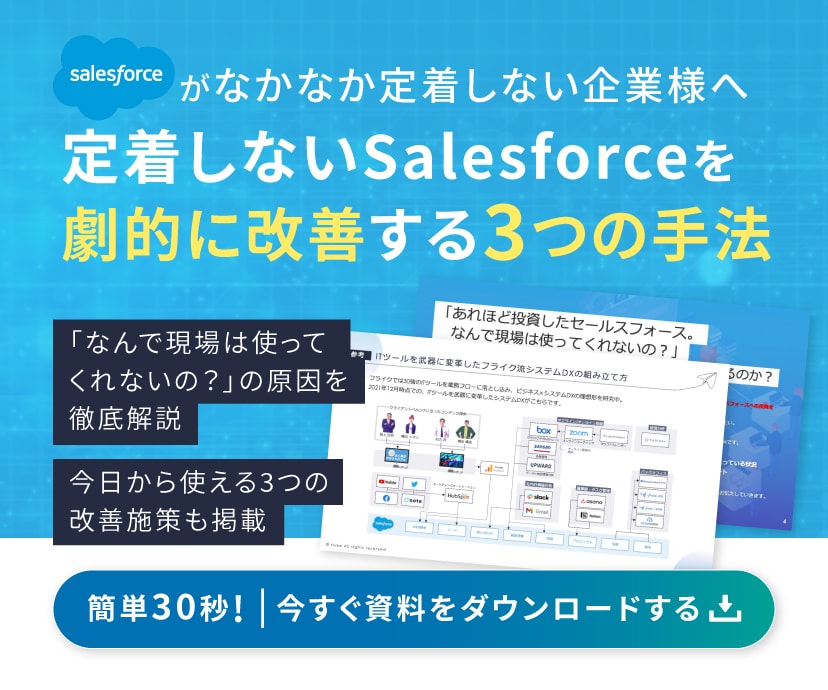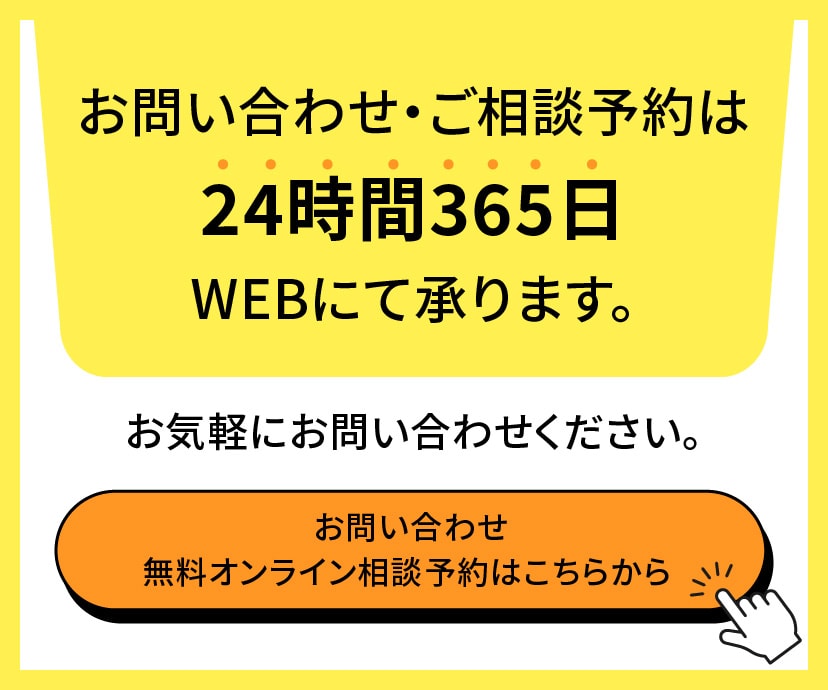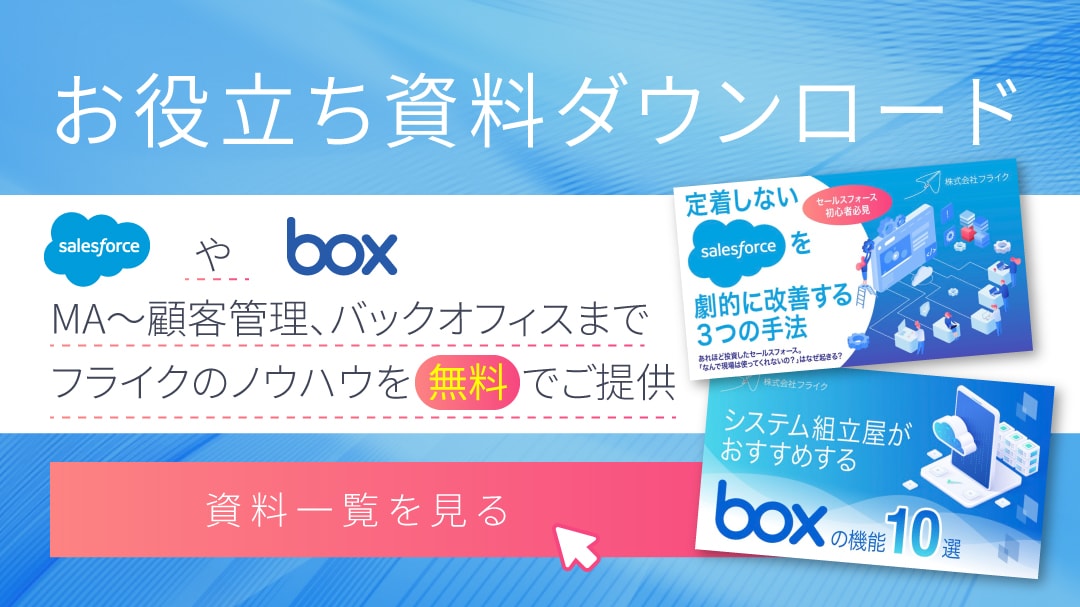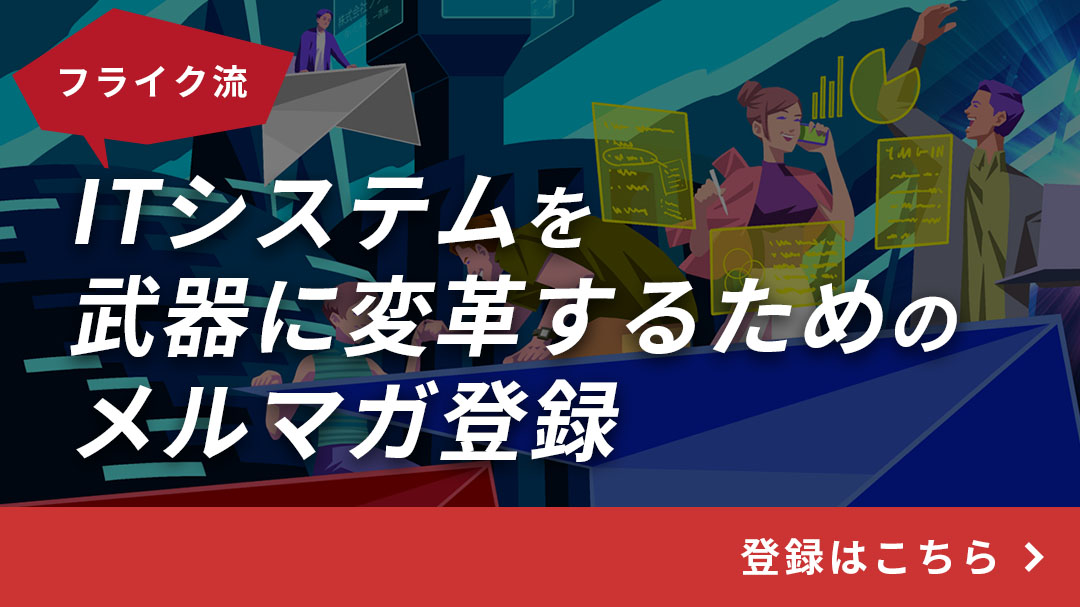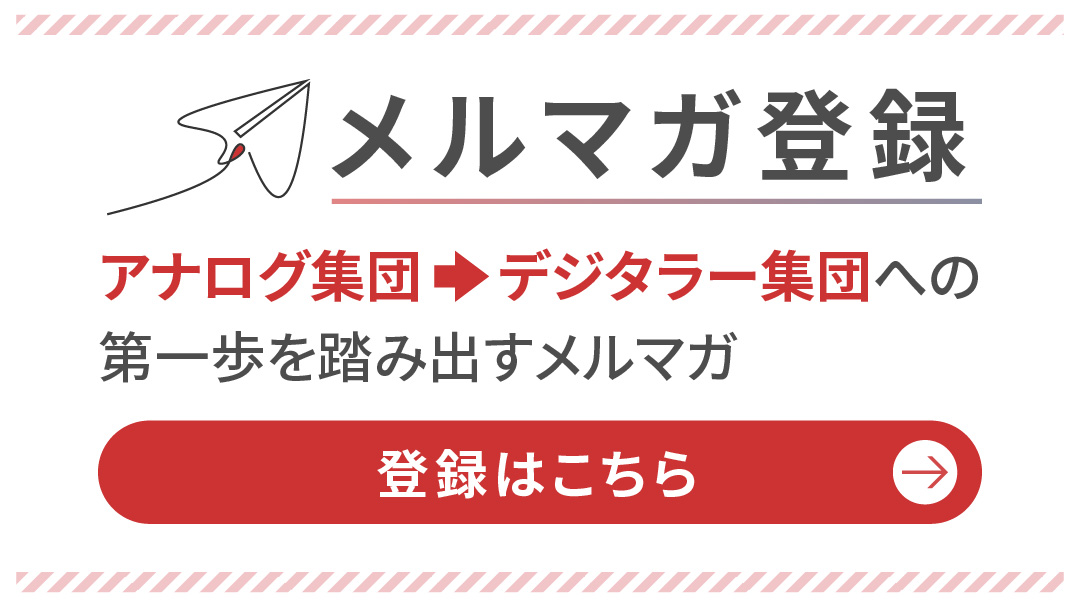ツール先行思考を捨てたシステム導入の極意 第三部:「ベンダー任せ」の落とし穴とツール選定のコツ
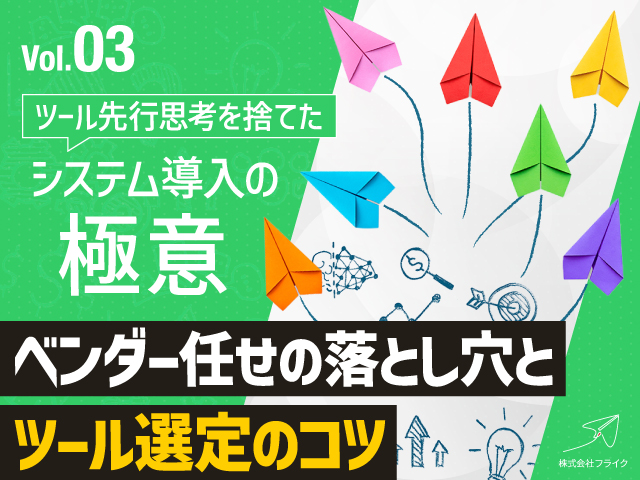
このブログでは、「ツール先行思考を捨てたシステム導入の極意」と題し、全4回にわたり「もう失敗したくないシステム導入・また失敗しないための業務設計とシステム設計」について解説していきます。
- 第一部:成功率52.8%の理由から紐解くシステム導入
- 第二部:ツール選定よりも大切な【業務設計】と【システム設計】
- 第三部:「ベンダー任せ」の落とし穴とツール選定のコツ
- 第四部:システム運用戦略とPDCAサイクルの重要性

今回は第三部ということで、「ベンダー任せ」の落とし穴とツール選定のコツを詳しく解説します。
突然ですが、皆さんはシステム導入においてこんな経験をしたことはありませんか?
- ITツールを導入したけれど、思ったように活用できず失敗した
- 営業のデモンストレーションでは魅力的に見えたが、契約後のサポートが想像と違った
- ITツールベンダーに紹介されたパートナー企業の対応にがっかりした
このような経験を経て、もう一度システム導入に挑戦しようとする方々が共通して抱いているのは、もちろん「もう、失敗したくない」という思いでしょう。
では、どうすれば自社にとって【本当に使えるITツール】を選べるのでしょう?
また、どのようにして信頼できるシステム開発企業やパートナー企業を見極めればいいのでしょう?
今回は、そうした疑問にお答えしながら、フライクが考える「もう失敗しないためのツール・パートナー選定のポイント」をご紹介します。
目次
はじめに:フライクのスタンス
はじめに、公平性を担保するため、フライクのスタンスをお伝えします。
弊社はSalesforce、Sansan、freee、HubSpot、Backlogなど、さまざまなITツールの導入・活用を得意としていますが、基本的にベンダーからの紹介案件はお断りし、一切受けていません。
もちろん、ビジネスの観点から見れば「紹介案件」は一定の価値があります。
しかし、ITツールベンダーからの紹介には、
「本当は別のITツールのほうが適していると思っているが、紹介元の手前、言えない」
「このツールを導入しても意味がないが、紹介元のメンツを潰すわけにはいかない…」
など、ベンダーにとって“不都合な真実”を言いづらくなるリスクがあります。
こうした“しがらみ”があると、クライアントにとって本当に最適な選択肢を提案できなくなってしまうため、弊社では「ITツール縛りありきの案件は受けない」というスタンスを貫いています。
(※紹介を受ける場合、弊社のこのスタンスをご理解いただいたうえでお引き受けしています)
「ベンダー任せ」にすると起こる3つの落とし穴
システム導入の際、多くの企業は誰も失敗など望んでいないでしょう。
そのためには、ツールに関する“正しい知識”を持っているベンダーに完全に任せておけば大丈夫!と思っている企業も少なくないと思います。
しかし、その考え方は非常に危険です。
フライクの見解として、「ベンダー任せ」にすることで失敗してしまう主な原因は、
大きく3つあると考えています。
【「ベンダー任せ」にすると嵌ってしまう3つの落とし穴】
- ツールやサービスは優れていても、最終的に「人(担当)」が関与するため、運要素がある
- ベンダーの魅力的なデモンストレーションに惑わされ、実際の導入後の運用を想定できていない
- パートナー選定の基準が甘く、紹介や評判だけに頼り切ってしまう
大前提として、もちろんベンダー側は「クライアント企業のシステム導入を失敗させよう」と思っているわけではありません。
しかし、ベンダーの立場とユーザー企業の期待には、本質的な乖離があることを認識する必要があります。
その乖離を解消するためには、まずITツールベンダーのビジネス構造を理解することが重要です。
詳しく見ていきましょう。
ツールやサービスは優れていても、最終的に「人(担当)」が関与するため、運要素がある
システム導入は、どれだけ優れたツールやサービスを選んでも、最終的には「誰がプロジェクトを担当するか」によって成功・失敗が左右されます。
- 担当コンサルタントやエンジニアのスキル・経験のばらつき
- ベンダー企業の中でも担当者のアタリ・ハズレの差が大きい
- プロジェクト開始時と後半で担当者が変わることによる齟齬(ジョブローテーションの影響)
例えば、契約時は経験豊富な担当者が対応していたのに、実際のプロジェクト進行では経験の浅い若手が主担当になるケースも珍しくありません。
また、ベンダー内部のリソース状況によっては、別の大規模案件に優秀な人材が割かれ、自社のプロジェクトには実績の少ない担当者が就くこともあります。
では、優れた担当者にめぐりあうためにはどのようにすれば良いのでしょう?
運に頼らず、プロジェクトを成功させるためには、事前の見極めが不可欠です。
ポイント①:契約前に「誰が担当するのか?」を確認する
営業担当者との打ち合わせだけで進めると、契約後に想定と違うメンバーがアサインされることもあります。契約前には、次のことに気をつけましょう。
- 営業担当ではなく、実際のプロジェクト担当者と事前に顔合わせをする
- 担当者の経歴・過去のプロジェクト実績を確認する
- 担当者変更があった場合の対応(事前通知・引き継ぎの仕組み)を明確にする
「この担当者なら大丈夫」と思っても、途中で交代するリスクもあるため、属人的にならない契約や引き継ぎルールを確認しておくことが重要です。
ポイント②:パートナー企業の選定基準を明確にする
ITツールベンダーによっては、専任の導入担当者を持たず、パートナー企業を紹介するケースがあります。
しかし、ベンダー側の紹介は「実績があるから」ではなく「取引関係があるから」「安く提供してくれるから」という理由で決まっていることも少なくありません。
そのため、紹介されたからといってそのまま任せるのではなく、自社にとって本当に適した企業かを見極める必要があります。
- 「なぜこのパートナーが選ばれたのか?」をチェック
- パートナー企業の過去の導入実績(業界・企業規模・改善業務・利用範囲など)をチェック
- パートナー企業のブログや動画などをしっかり確認し、プロジェクト方針を確認する
- 複数のパートナーと比較検討し、相性の良い企業を選ぶ
導入後に「思っていたサポートが受けられない」とならないよう、紹介されたからといって安易に選ばず、自社の基準で選定することが重要です。
ポイント③:プロジェクトの進め方を提示し、「担当者任せ・丸投げ」にしない
システム導入を成功させるには、ベンダー任せにするのではなく、あくまで自社が主体となってプロジェクトを進めることが必須条件です。
ベンダーや導入パートナーはあくまで「支援者」であり、主導権を握るのはユーザー企業自身です。
担当者のスキルや経験に依存しすぎると、プロジェクトが迷走するリスクが高まります。
「この人に任せれば大丈夫」ではなく、「誰が担当になっても成功できる進め方を提示すること」が重要なのです。
- 導入目的・スケジュールを明確にし、プロジェクトのゴールを提示する
- 定期的な進捗レビューを実施し、課題を早期に洗い出す
- 業務フローや要件をドキュメント化し、引き継ぎリスクを軽減する
「プロジェクトがどうなるかは担当者次第」ではなく、「どんな担当者でも成功できる仕組み」を作ることです。
担当者に頼るのではなく、自社全体が主体的にプロジェクトを管理する仕組みを整えることで、成功の確率を格段に高めることができます。
ベンダーの魅力的なデモンストレーションに惑わされ、実際の導入後の運用を想定できていない
契約前の商談で見るデモンストレーションは、美しく洗練されています。
そのデモンストレーションを見て、多くの企業は「このツールならうまくいきそう!」と心が踊ってしまいますが、それは意図的な設計になっているから当たり前のことなのです。
しかし、実際に導入してみると「思っていたのと違う」というケースが後を絶ちません。
- デモ環境は最適な設定がされているが、実際の業務に落とし込むと運用が複雑になる
- 営業担当の説明ではスムーズに見えたが、カスタマイズが必要なことが判明し、追加コストが発生
- 導入後のオペレーションやユーザー教育の難易度を見落としていた
ベンダーが提供するデモンストレーションは、「ITツールを魅力的に見せるための演出」です。
一見「標準機能」の範囲で完結しているように見えても、実際の業務では細かな調整やカスタマイズが必要になることが多く、いざ導入してみると「データ連携」「業務フローの変更」「運用負荷」など、デモンストレーション上では見えないような機能が、導入した後で問題になってしまうこともあります。
ITツール導入の失敗を防ぐには、ベンダーの提案やデモンストレーションを鵜呑みにせず、自社の業務に本当にフィットするかを見極めましょう。
ポイント①:自社の課題を整理し、発生前後の業務フローを明確に伝える
ベンダーに対して、「何に困っているのか?」だけを伝えるのはNGです。
その課題がどの業務フローの中で発生し、どのような影響を与えているのか?を明確に説明しましょう。
【具体的な伝え方】
● NG例:「データの入力が面倒なので、自動化したい」
→解決策がツール依存になりやすい
● OK例:「顧客対応の情報が営業、カスタマーサポート、バックオフィスでバラバラに管理されており、二重入力が発生している」
→「この業務のどこにツールを活用すべきか?」を具体的に検討できる
ポイント②:同業他社だけでなく、異業種・異業界の解決事例を聞く
ベンダーは一般的に、同業他社の成功事例を前面に出して提案を行います。
しかし、業界が違っても共通する課題は多く、異業界の解決事例のほうが有益なヒントになることもあります。
そのため、ベンダーに質問する際は次のようなことを聞いてみましょう。
- 「この課題を解決するために、異業種ではどのようなツールの使い方をしているか?」
- 「業界に依存しないベストプラクティスはあるか?」
同じ業界の事例だけで判断すると、「業界の常識」に引っ張られ、本当に最適なツールを見逃してしまう可能性があります。
異業種・異業界の事例を参考にすることで、より柔軟なシステム活用の選択肢を持つことができるのです。
ポイント③:デモンストレーションで「標準機能」と「オリジナル機能」の線引きを明確にする
先ほども少し触れましたが、ベンダーのデモンストレーションでは、標準機能と見せかけて追加開発・カスタマイズされたオリジナル機能が混ざっていることがあります。
そのため、デモンストレーションを見る際は次のことに気をつけましょう。
- 「ここまでが標準機能で、ここからがオリジナル機能か?」
- 「オリジナル機能は開発費用はいくらかかるか?」
- 「開発にどれくらいの期間が必要か?」
標準機能だけで運用できるのか。
それとも追加開発が必須なのかを明確にすることで、導入後に想定外のコストやスケジュールの遅延が発生するリスクを回避できます。
パートナー選定の基準が甘く、紹介や評判だけに頼り切ってしまう
パートナー企業(開発ベンダー、導入支援企業、SIer)の選定において、「敏腕のカスタマーサクセスを紹介されたから」「評判がいいから」などという理由だけで決めてしまうと、失敗のリスクがあがります。
なぜなら、ITツールベンダーのカスタマーサクセスの目的は「ユーザーの業務効率化やビジネス成功」ではなく、「自社サービスの利活用促進(追加契約)」や「契約継続(解約防止)」にあるからです。
多くのITツールがサブスクリプションモデルを採用しており、契約が続く限り課金が発生するため、ITツールベンダーであるサービス提供企業側が「継続率向上」を重視しています。
そのため、サポートは手厚くても、本質的な業務改善には踏み込まないことが多く、極端な話になりますが「ツールは使われなくても解約さえなければ問題ない」という企業すら存在しているというのが現状です。
また、次のようなデメリットもあります。
- 紹介元のITツールベンダーに配慮し、最適な選択ができなくなる
- 評判が良い企業でも、自社の業界・規模・業務に適した実績があるとは限らない
- 実際の担当者レベルでの相性を見極めないまま契約してしまう
そのため、選定時はパートナーに対して何を期待するのかを明確に定めることが重要です。
カスタマーサクセスと協力することで期待できるのは、次の3つの観点に限られます。
- 標準的な利用方法の説明(基本機能の活用方法)
- 自社の課題に即した設定・運用のアドバイス
- 他社での利活用事例の共有
そして忘れてはいけないのが、カスタマーサクセスの主な目的は「契約更新」「追加契約」であるということです。
この点を踏まえ、契約更新の基準と追加契約の判断軸を事前に決めておくことも重要です。
● 契約更新をする条件・しない条件を決める
→実際に業務改善が進んでいるか?
→ツールが想定した効果を発揮しているか?
● 追加契約は本当に必要かを冷静に判断する
→ただ「便利そう」だから契約するのではなく、現行業務と導入コストを比較する
→異なるサービスを提案された場合、業務全体の視点で本当に必要かを慎重に検討する
パートナー選びは、ツール導入の目的と効果を常に意識し、本当に必要かどうかを見極めましょう。
フライク流ITツール・パートナー企業の選び方
フライクは、社内で35以上のITツールを活用しており、これまでに多くの企業からの提案を受けてきました。
また、私自身もキャリアの中でSalesforce、Box、freeeなどのITツール販売を経験しているため、「売る側」としての視点と「使う側」としての視点の両方を持っています。
その経験から言えるのは、「どのツールを選ぶか」というのも大切ですが、それ以上に「誰と進めるか」もシステム導入の成功に直結するということです。
しかし、多くの企業が「評判が良いから」「ベンダーに紹介されたから」という理由でツールやパートナーを選び、結果として「導入したものの使いこなせない」「想定以上にカスタマイズが必要だった」という事態に陥っています。
そこで、フライクでは「ツールありき」ではなく、「業務にフィットするパートナーとツールの選定」を重視しています。
私たちが実践するITツール・パートナー企業の選び方を、余すことなくご紹介しましょう。
ITツールの選び方:ツールの特性と導入後の運用を見極める
ツール選定時には「導入すること」が目的にならないよう「業務を円滑に進めるためのツールか?」を基準にチェックすることが不可欠です。
【失敗しないITツールの選び方〜自社実践内容〜】
1. ツールの紹介とデモンストレーションを受ける
a. 標準機能とカスタマイズ機能の範囲を明確にし、業務に適合するかを確認する
2. 他社ツールを2〜3種類比較する
a.「本当にこのツールが最適なのか?」を判断するため、複数ツールを比較検討する
b.最初に本命ツールのデモンストレーションを受けるのがおすすめ
– 他のツールと比較しやすくなり、検討基準が明確になる
3. カスタマイズされている機能があれば、どこからどこまでかを確認する
a. 追加開発の必要性、費用感、スケジュールを事前に把握する
4. 実環境のデータで確認する
a. 秘密保持契約(NDA)を締結した上で、自社の本番データを使ってデモンストレーションを実施する
b. 業務の流れに沿った動作確認ができ、導入後のギャップを減らせる
5. 他のシステムとの連携ができるかを確認する
a. 「単体では優秀でも、既存システムと連携できず業務が非効率になる」事態を防ぐため、連携性を重視
b. 「データエクスポート可能」「API連携対応」と言われても、仕様書を確認しないと実際には使い物にならないケースがある
導入後に「想定と違った」「運用が回らない」とならないよう、実際の業務との適合性を徹底的に確認しましょう。
パートナー企業の選び方:「誰と組むか」で導入成功が決まる
パートナー企業は、単なるシステム開発の外注先ではなく、導入を成功に導く“伴走者”。
単なる「システムを初期設定する業者」ではなく、「業務を理解し、共に導入を進める存在」です。
適切なパートナーを選ぶことで、システム導入のスムーズな進行と、運用後の成功確率を大きく高めることができますが、そのためには慎重な選定が欠かせません。
ここでは、フライクが実践している失敗しないパートナー企業の選び方をご紹介します。
【失敗しないパートナー企業の選び方〜自社実践内容〜】
1. プロジェクトに関わるメンバーを確認する
a. 契約前に、実際に担当するメンバーと顔合わせを行い、スキルや相性を確かめる
b. 単に「企業としての実績」ではなく、「担当者の経験・専門性」を見極めることが重要
c. コミュニケーションの雰囲気、課題への理解度を確認する
る
d. WEB会議のみで進める場合は、ネットワーク環境やカメラ・音声の質もチェック
2. SNSやブログ、動画などの情報発信を確認する
a.企業の方針やノウハウ、業界への理解度をチェック
b.実際に担当する可能性がある人物のSNSも調べ、考え方や発信内容を確認
3. 導入実績を確認(同業他社だけでなく、異業種の事例もチェック)
a. 業界特化の企業だから安心ではなく、課題解決のアプローチが適切かを見極める
b. 異業種でも同じ課題を解決した実績がある企業は、視野が広く柔軟な対応が期待できる
4. サポート体制と契約内容(請負契約or準委任契約)を明確にする
a. トラブル発生時の対応範囲、責任の所在を事前に確認する
b. 追加対応が必要になった場合の費用感、変更手続きの流れを把握しておく
たとえば、経営層は「コストと効果」、IT部門は「技術力とサポート力」、経営企画部は「業務適合性と実行力」といったように、それぞれの視点でしっかりチェックしながら、自社の課題に適したパートナーを選びましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は「「ベンダー任せ」の落とし穴とツール選定のコツ」というテーマで、IT訴訟やITトラブルからの教訓を活かし、要求定義・要件定義の重要性について解説しました。
システム導入の失敗を防ぐためには、単に「良いツールを選ぶ」だけでは不十分です。
- 「誰がプロジェクトを担当するのか?」
- 「導入後の運用をどこまで想定できているか?」
- 「パートナー選定の基準は適切か?」
これらをしっかりと見極め、「ツールありき」ではなく「業務にフィットする形で導入する」という視点を持つことが、成功の鍵となります。
次回の第四部では「システム運用戦略とPDCAサイクルの重要性」をテーマに、システム運用における具体的な進め方についてさらに掘り下げていきます。
ぜひ、そちらも合わせてお読みください。
このブログを参考に、皆さんのシステム導入成功につながりますように。
NEW ARTICLES