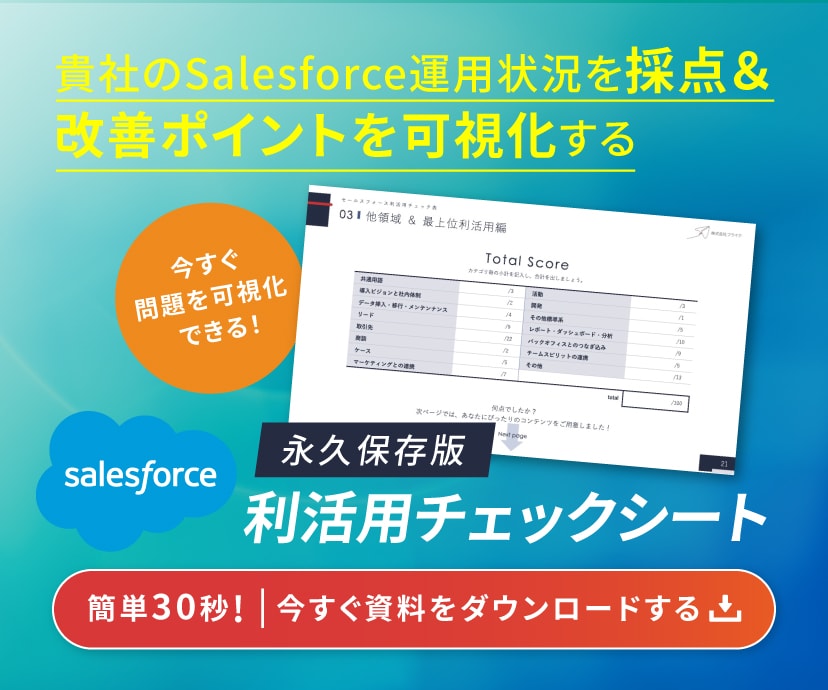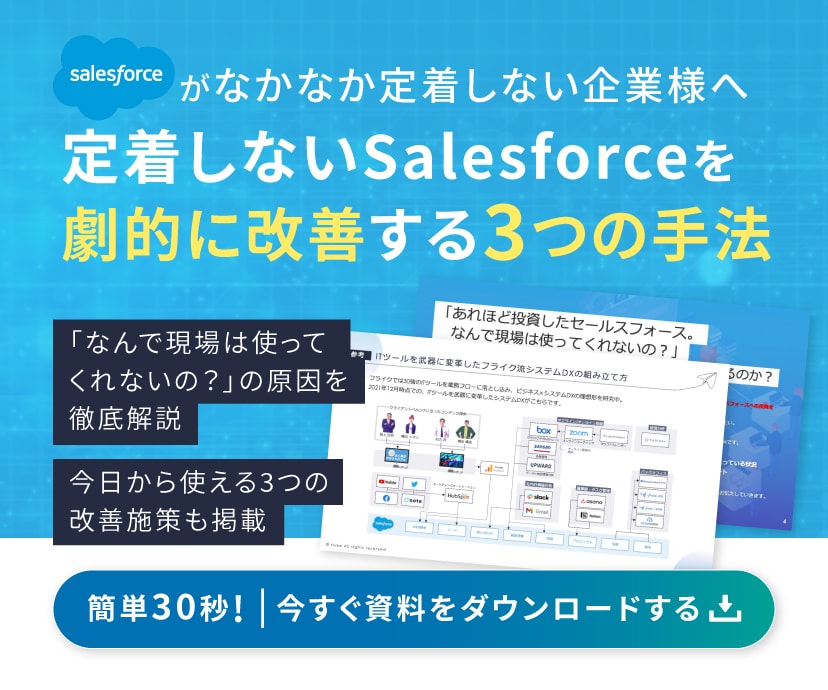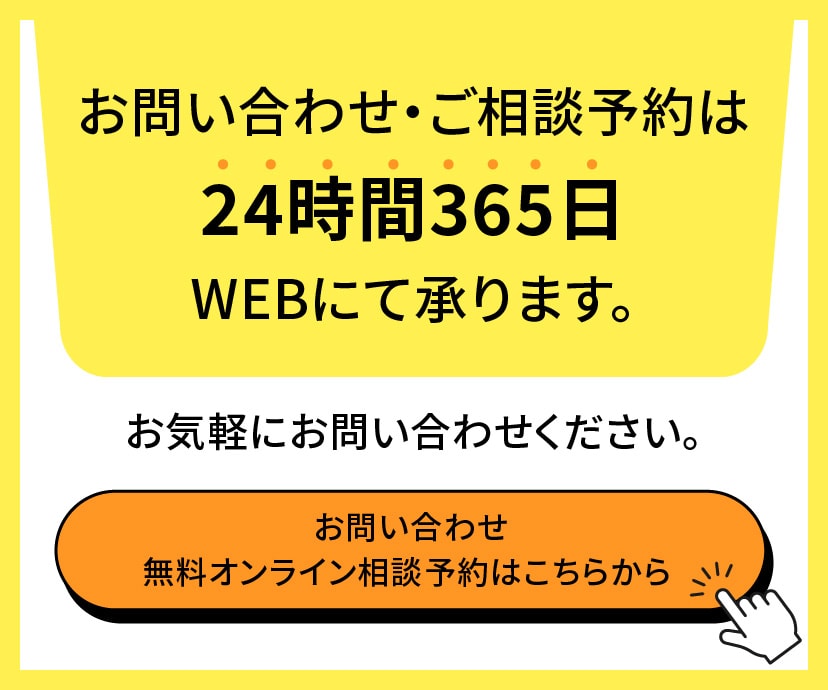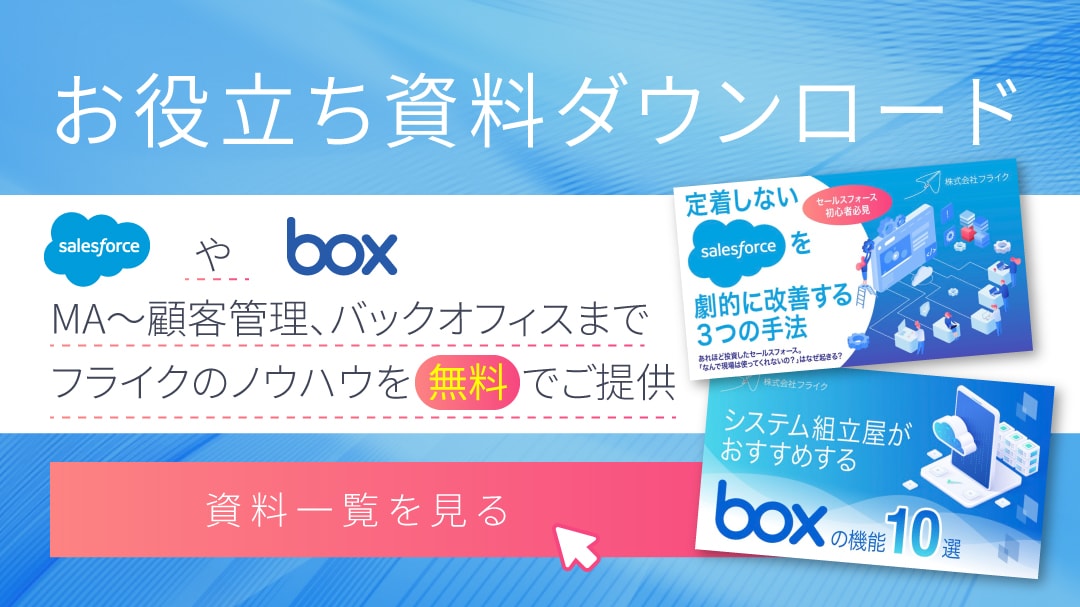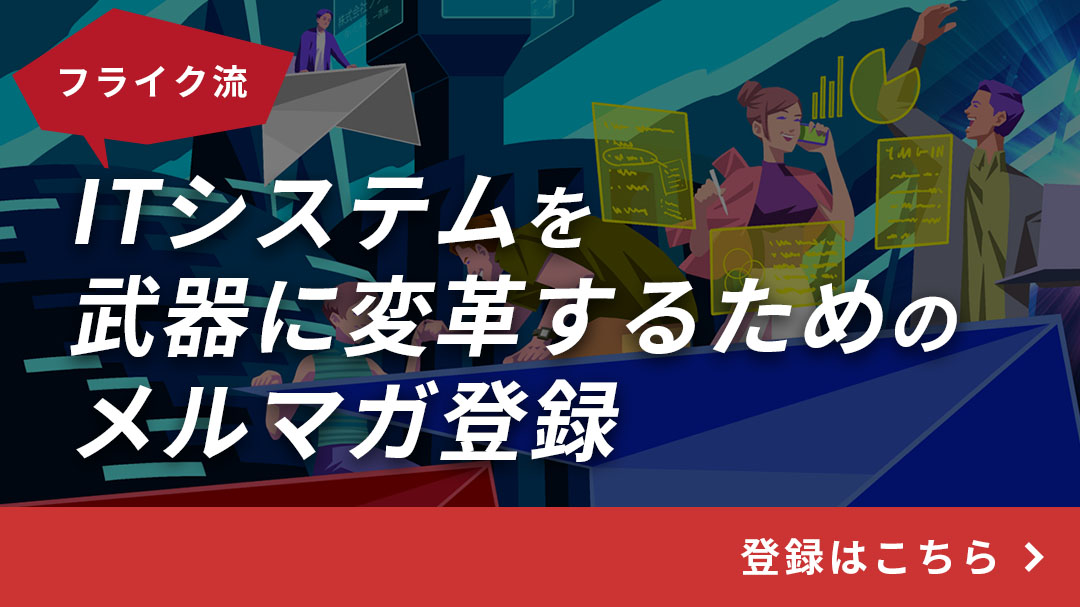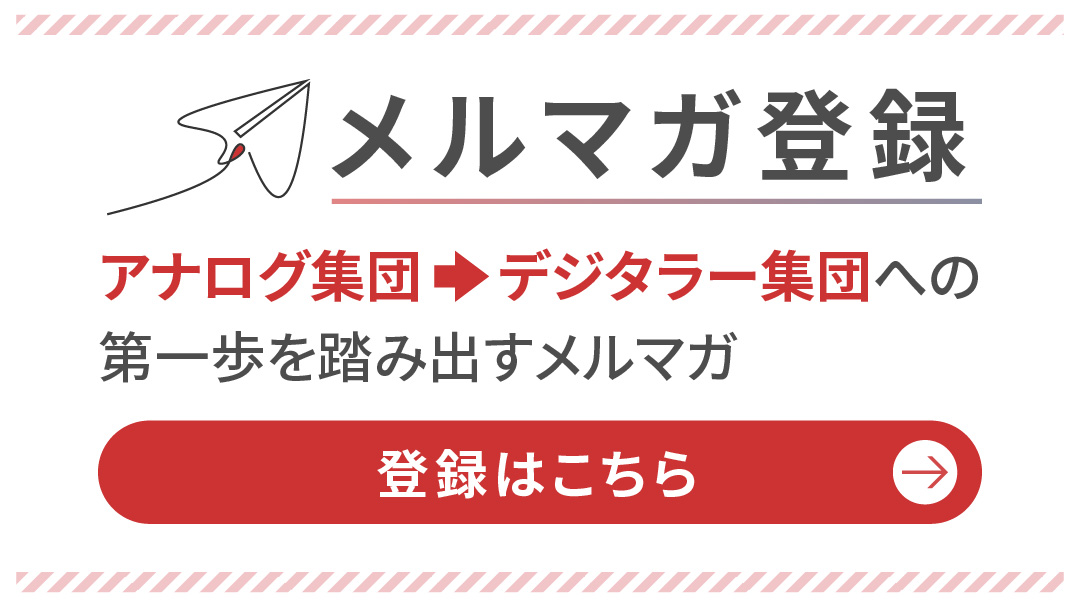ツール先行思考を捨てたシステム導入の極意 第四部:システム運用戦略とPDCAサイクルの重要性
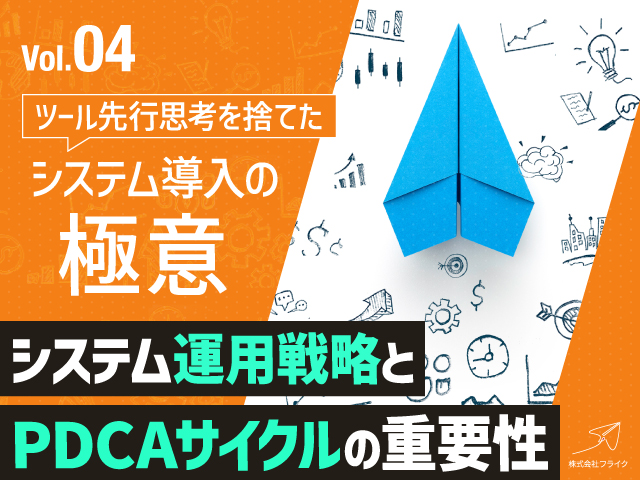
このブログでは、「ツール先行思考を捨てたシステム導入の極意」と題し、全4回にわたり「もう失敗したくないシステム導入・また失敗しないための業務設計とシステム設計」について解説していきます。
- 第一部:成功率52.8%の理由から紐解くシステム導入
- 第二部:ツール選定よりも大切な【業務設計】と【システム設計】
- 第三部:「ベンダー任せ」の落とし穴とツール選定のコツ
- 第四部:システム運用戦略とPDCAサイクルの重要性

今回は第四部ということで、システム運用戦略とPDCAサイクルの重要性を詳しく解説します。
本ブログを参考にしながら、「失敗しないシステム導入・業務設計のイメージ」をしっかりつかんでいただければ幸いです。
目次
システム導入は「ゴール」ではなく「スタート」
システムを導入し、いざ運用していくという段になって、このような経験をしたことはありませんか?
- 「システムを業務に合わせたはずなのに、業務が変わって使いづらくなった」
→せっかく作ったのに現場で結局Excel対応に逆戻り - 「導入費用だけで予算が尽きて、改修したくてもお金がない」
→“使いにくいシステム”を、我慢しながら使うのが当たり前に - 「社内で直せると思ったら無理だった。でもベンダーに頼むと高いうえに遅い!」
→結局、動かせないシステムと高額な外注費にモヤモヤ - 「担当者が異動・退職して、誰もシステムの構造がわからない」
→ブラックボックス化して、誰も触れず“使いこなせないシステム”ができてしまう - 「紹介されたパートナーに任せたら、導入後に音信不通に!?」
→「保守はやっていません」と言われて呆然。新しい支援先探しに右往左往
まず始めに言わせていただきますと、システム導入完了=「ゴール」ではなく、あくまでもスタートラインに立っただけです。
「システム導入したから、全ての業務が滞りなく進むようになる!」
「あとはそれぞれのチームに任せておけばOK!」
ということではなく、その後の運用についても考えなければなりません。
ただし、こうした運用失敗を事前に100%防ぐ方法はおそらくないでしょう。
その理由は、2つ考えられます。
【システム運用失敗を事前に回避できない理由】
- どれだけ準備しても、導入後に業務のズレや改善点は必ず発生する
- 「計画通りに運用できるはず」という思い込みが、システムの形骸化を招く
それぞれを詳しく見ていきましょう。
どれだけ準備しても、導入後に業務のズレや改善点は必ず発生する
いくら事前に業務設計やシステム設計を行っても、実際に現場で使い始めると「こうしてほしい」「やっぱり使いづらい」という声が必ず出てきます。
なぜかというと、企業やビジネスは“生き物”であり、日々成長・変化し続けているからです。
たとえば新たなサービスが始まったり、業務の進め方が変わったり、顧客対応のフローが進化するのは当然のこと。
だからこそ、「導入したら終わり」ではなく、「導入後も柔軟に手を加えていく」ことが大前提になります。
この認識がないと、せっかく導入したシステムがあっという間に“使われないシステム”となってしまい、導入の意味がなくなってしまうのです。
「計画通りに運用できるはず」という思い込みが、システムの形骸化を招く
次に、「システム導入時と同じ状態で、ずっと使い続けられるはず」という思い込み(バイアス)を捨てる必要があります。
ビジネスもサービスも人も業務も、必ず想定外のことが起こるものです。
だからこそ、「計画と違っても仕方ない」「随時見直そう」という柔軟な姿勢が欠かせません。
この意識がなければ「業務が変わってもシステムはそのまま」となり、使われなくなる→形骸化という失敗の道を進むことになります。
システムは“変わることを前提”に運用設計すべきなのです。
だからこそフライクでは、「完璧に作って終わり」ではなく、「必ず失敗やズレが起きる前提」でシステム運用を考えることが重要だと考えています。
導入して終わりにしない!“使われ続ける”ためのシステム運用5ヶ条
前章でお伝えしたように、システム運用の失敗を事前に完全に回避することは難しいのが現実です。
とはいえ、「それでは困る!」という方が大半でしょう。
安心していただきたいのは、導入前から適切な準備や仕組みを整えておけば、運用上のトラブルや失敗リスクを限りなくゼロに近づけることができるということです。
さらに、もし問題が起きたとしても、素早くリカバリーできる体制を作ることが可能です。
そこで今回は、フライクが提唱する導入後も“現場が使い続けられるシステム”を育てるための運用5ヶ条をご紹介します。
定期的にシステム変更ができるように、設計書や仕様書を常にアップデートする
システムを「入れて終わり」にしないためには、業務やシステムの変更を常に設計書・仕様書に反映させることが欠かせません。
そのために必要な具体的な取り組みは以下のとおりです。
①-1 システム導入時に「業務設計書」「システム設計書」を必ず納品物に入れる
● 導入時の契約や納品物に必ず「業務設計書」「システム設計書」を含めることを確認。
● 「ないまま運用開始」は絶対にNG!
-設計書がなければ、いざ業務やシステム変更が必要になったときに 「どうやって直せばいいかわからない」
→システムが使われなくなるリスクが跳ね上がります。
①-2 設計書をアップデートするための「運用ルール」を作る
● 現場からのリクエストや改善依頼を受けたときは、
-業務フローのどこが変わるのか?
-システムのどの機能・仕様をどう変えるのか?
-誰がどんな意思決定をして変更に至ったのか?
→これらを「業務設計書・システム設計書」に必ず記載するルールを作ります。
● 「言われたから直した」ではなく、直した経緯を詳細に残すことで、社内全体で変更を理解・共有できます。
①-3 業務設計書・システム設計書の保管と管理ルール
● 設計書類は、誰でも参照できる共有フォルダやクラウド(SharePoint、Box、Google、Driveなど)に格納。
● ただし、編集できるのは責任者や情報システム部など限られたメンバーに限定。
● 変更履歴も管理し、「いつ、誰が、なぜ、どう変えたか」が追える状態に。
社内メンバーが「自分たちでできること」を明確にし、できる人を育てる
システムを外部任せにせず、社内で主体的に運用・改善していくためには、「自分たちでできること」を明確にし、実行できる人材を育てることが重要です。
②-1 社内で担うべき領域を具体的に定める
システム運用・開発における各工程の中で、「どこまでを社内で行うか」をあいまいにせず明文化しましょう。
②-2 必要な人材を「採用するか・育成するか」を明確に決める
「この範囲は社内でやる」と決めたら、それを担える人材をどう確保するかも検討しましょう。
● 外部から採用するのか?(即戦力人材が必要な場合)
● 既存メンバーを育成するのか?(長期的な視点で内製化を進める場合)
この時、重要なのは「採用コスト」「育成コスト」を含めた人材戦略として社内合意を得ることです。
特に人事部門や経営層と連携し、「誰をどう育てる?」「どのスキルまで求める?」をしっかり話し合いましょう。
②-3 スキルマップを作る
社内にどんなスキルがあって、どこが不足しているかを「見える化」するために、スキルマップを作ることも有効です。
誰がどのツール・工程をカバーできるのか?
今後、どこを育てていく必要があるのか?
「属人化」や「できる人が辞めたら終わる」という状況を防ぐためにも、社内で対応できる領域を見える化し、チームで分担できる体制を作りましょう。
社外に依頼する場合の「依頼方法」を明確にし、ルール化する
システム運用の中で、どうしても社外パートナーに依頼が必要な場面は出てきます。
しかし、ここがあいまいなままだと「なんとなく依頼」や「毎回ゼロから説明」で時間もコストも無駄が増え、結果として対応の質もバラつき、運用の品質が下がる原因になります。
そこで大切なのが、「どんなときに」「どう依頼するのか」を明確なルールとして整えておくことです。
以下、具体的な方法をお伝えします。
③-1 社外に依頼するルールを決める
依頼するときは、ただ「直してください」「変えてください」ではなく、背景・目的・要件をセットで伝えることが重要です。
依頼時の記載例として、以下の情報を必ず含めるようルール化します。
【依頼時に必ず伝えるべきこと】
● 業務の背景:「なぜ今この依頼が必要なのか」「どんな課題や変化が起こったのか」
● 変更前の業務:「もともとこういう流れ・運用だった」
● 変更後の業務:「これからこういう流れ・運用に変えたい」
● そのためにシステムに必要な変更:「だから、この機能・画面をこう直してほしい」
これをテンプレート化し、毎回「何を」「なぜ」「どう直すか」がセットで依頼されるようにしておけば、社外パートナーも正確・迅速に対応しやすくなり、無駄な工数削減にもつながります。
③-2 設計書(業務設計書・システム設計書)の更新ルールを決める
よくあるミスが、「システムだけ変わって、設計書が古いまま」になってしまうことです。
システムと設計書の不一致=ブラックボックス化のはじまりなので、これを防ぐために設計書更新の役割分担を明確にする必要があります。
【設計書更新のルール例】
こうすることで、「誰がどこまで責任を持つのか」が明確になり、設計書とシステムのズレを防ぐことができます。
【これら2つを遵守することのメリット】
● 依頼のたびに無駄な打ち合わせが減る(背景や目的が明確なため)
● 見積・対応スピードが速くなる
● 誤解やズレが減り、手戻りや追加費用が防げる
● システム変更後の設計書更新が必ず行われ、ブラックボックス化を防げる
これが徹底できれば、「毎回言わないとわからない」「設計書がないから動かせない」といったシステム運用の負のサイクルから抜け出せます。
システム運用費用(ランニングコスト+人件費)を定期的に見直す
繰り返しお伝えしますが、システムは「入れて終わり」ではなく、日々の業務を支える重要な“ビジネスパートナー”であり、システムの運用にかかる費用も「一時的なコスト」ではなく、人件費と同じように継続的な投資と考えるべきなのです。
しかし、導入初期と安定運用フェーズではかけるべきコストのバランスも変わります。
そのためにも、定期的にコストを見直し、必要なところに集中投資しながら、無駄な費用は削減していくことが大切です。
④-1 導入初期は「人件費と同じ」と考え、手厚い運用費用を確保する
● 導入初期は“教育コスト”と割り切り、手厚く費用を確保するのが基本。
● システムも現場も「まだ不慣れ」な時期だからこそ、外部支援や追加改修の予算はしっかり持つべきです。
● システムは「毎日の仕事を支える存在」なので、人件費と同じ感覚でコストを考える必要があります。
④-2 社内メンバーの育成・リーダーの定着に応じて、徐々にコストを適正化する
● 社内のシステム担当者や現場の推進リーダーが育ってきたら、外部依存を減らして内製化によるコスト削減を進めることも重要です。
● いきなりゼロベースで自社完結を目指すのではなく、段階的に社内でできる範囲を広げていく形が現実的。
● ただし、「無理にコストカット」ではなく、負担が適正かどうかを継続的に見直すことがポイント。
④-3 半年ごとに運用コストを見直す
● システム導入は「1回決めたら固定」ではなく、半年ごとに見直しのタイミングを持つことを推奨。
● 見直すべきポイント例:
-外部パートナーに依頼している内容と費用
-社内対応できる部分の拡大可能性
-新たな業務変化により必要になった改修費用
-想定外に発生しているコスト
定期的なレビューをすることで、現場感覚に合った運用が続けられます。
④-4 「スモールスタート」で広げる場合はアウトソーシングも選択肢
● 最近のシステム導入では「まず一部だけ導入して、徐々に展開する」スモールスタートが一般的です。
● この場合、業務フローやシステムも段階的に広がっていくので、設計書のアップデートコストも発生します。
● 「スモールスタート+段階的展開」型の場合は、設計書の更新や軽微な設定変更などを外部アウトソーシングとして考えることで、社内リソースの負担を減らす工夫も大切です。
経営陣や役職者がWeekly・Monthlyでシステムを意識するタイミングを持つ
システムは、導入後に現場の業務がスムーズに回り出すと経営陣・役職者からは「使われている実感」が薄れ、“ただのランニングコスト”に見えてしまい、「なんでこんなにお金がかかっているのか理解できない」というところから、「よくわからないから放置」につながりやすいのです。
ですので、経営層・役職者がシステムを定期的に意識する場づくりを行いましょう。
⑤-1 「システム活用の成果・課題」を定期的に経営陣に報告する
システム導入による業務改善効果(工数削減・売上貢献・リスク低減)を、数値や事例で隔週・月次報告。
「こんな改善があった」「今こんな課題が見えている」と現場の声を経営層と共有することで、予算や体制の支援も得やすくなる。
● 報告例
-「月●時間の工数削減」「●件のエラー防止」「売上管理の迅速化」など。
⑤-2 「経営に関わるKPI・指標」をシステムから定期レポート
● 経営層や役職者が関心を持つ指標(売上、業務進捗、コスト管理など)を、システムから自動レポート。
● システムが“意思決定の土台”になっていることを日常的に体感してもらう。
● 単なる「業務ツール」ではなく「経営情報の基盤」として位置づける工夫が重要。
⑤-3 「システム活用・改善」を定例会議の議題に固定化する
● Weekly/Monthlyの経営会議、部門会議の議題に「システム活用状況・課題・改善計画」を必ず入れる。
● 現場と経営が継続的にシステムについて会話する仕組みを持つことで、形骸化を防ぎ、アップデートの意思決定がスムーズに。
● 「最近システムどう?」ではなく、「今月の報告」のように仕組み化するのがポイント。
これらの工夫を通じて目指すべきは、システムのランニングコストや運用コスト、関わる社内外の人件費を「単なるコスト」ではなく「事業を支える必要経費」として、経営陣が自然に認識できる状態を作ることです。
そうなって初めて、システムが「入れて終わりの箱」ではなく、会社の成長や競争力を支える武器として育ち続ける運用の仕組みが実現できます。
まとめ
いかがでしたか?
これまで全4部にわたって「ツール先行思考を捨てたシステム導入の極意」 として、「なぜ失敗するのか」「どうすれば失敗を防げるのか」について、体系的にご紹介してきました。
どんなに高額なシステムも、どれだけ最先端のツールも、運用がうまくいかなければ価値を生み出すことはできません。
むしろ「形骸化」や「ブラックボックス化」が進むと、現場も経営もシステムを負担に感じ、“使われない”投資になってしまう危険すらあります。
だからこそ大切なのは、システム導入後も継続的に改善・改修を回す前提で、運用戦略を立てること。
そして、経営陣から現場まで「システムも業務も変化する」ことを受け入れ、柔軟に対応できる組織づくりが不可欠です。
もし、「この内容を自社でどう落とし込めばいいか?」「自社の状況で何から始めればいいか?」と悩まれた場合は、ぜひお気軽に私たちフライクまでご相談ください。
一緒に “失敗しないシステム導入” を実現するためのお手伝いができれば幸いです。
このブログを参考に、皆さんのシステム導入成功につながりますように。
NEW ARTICLES